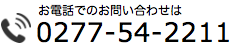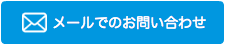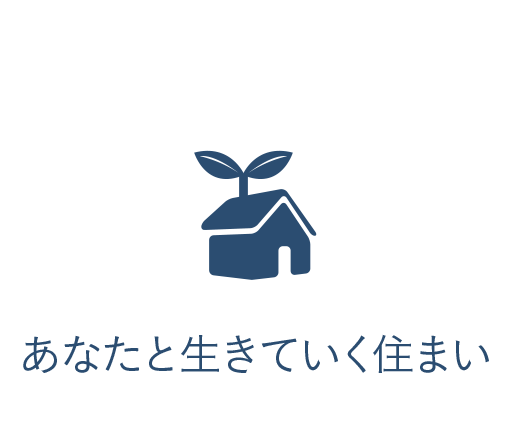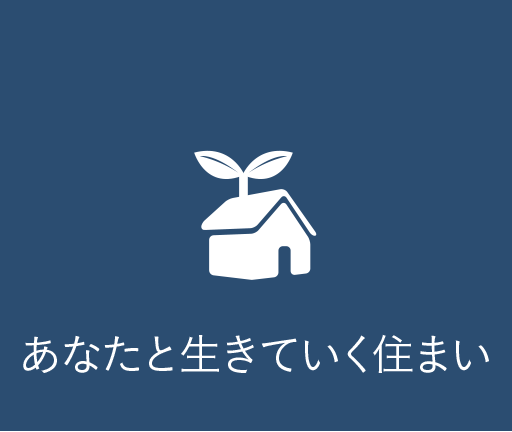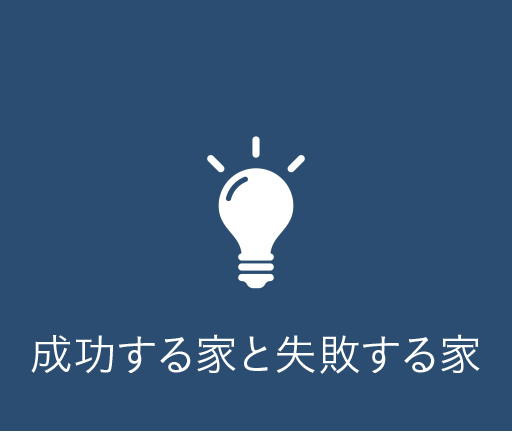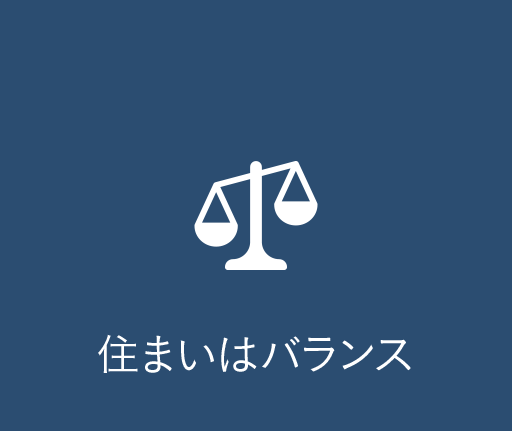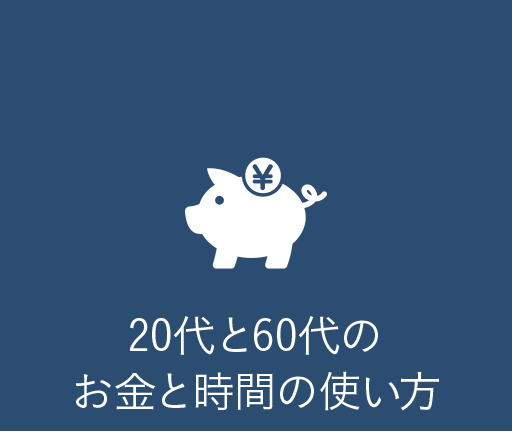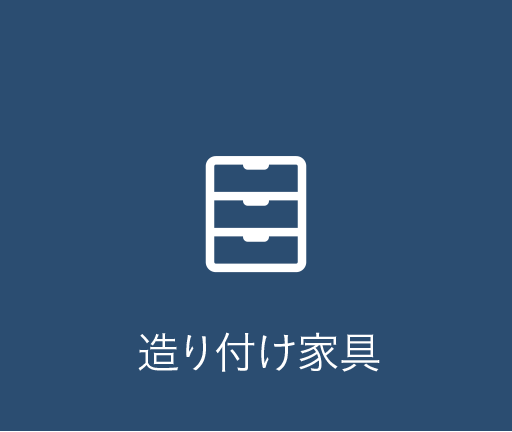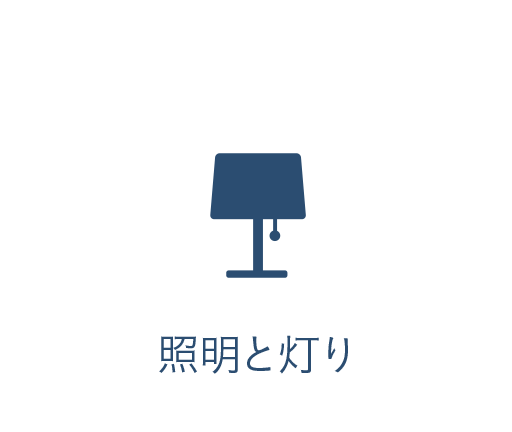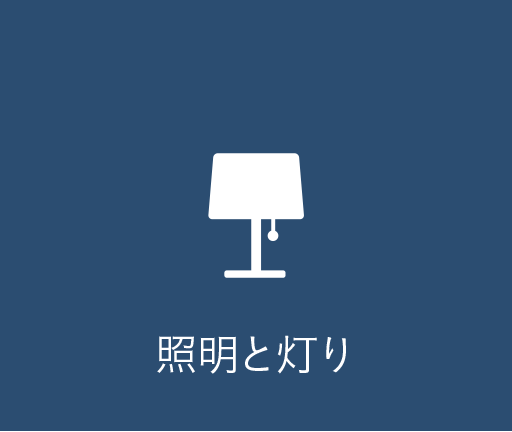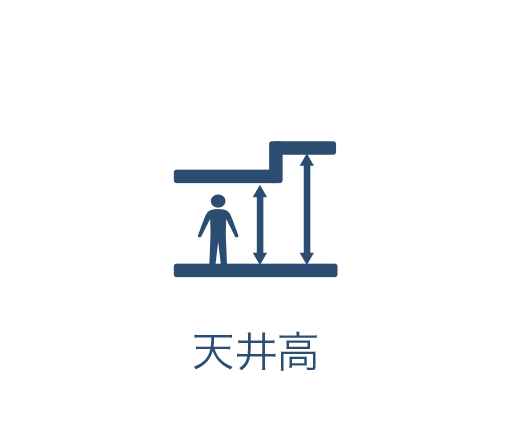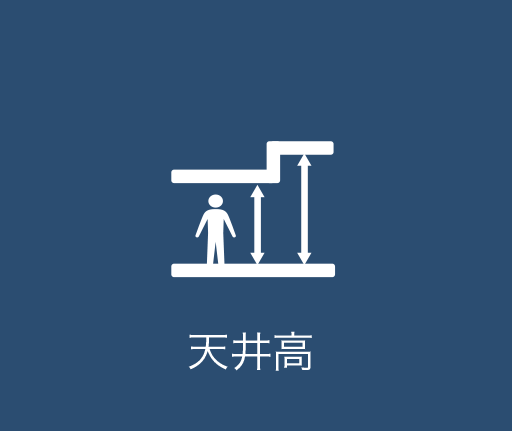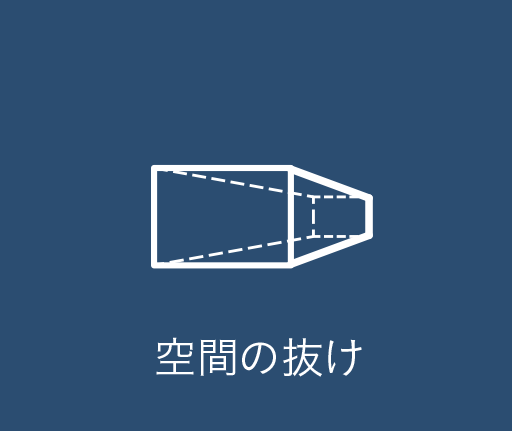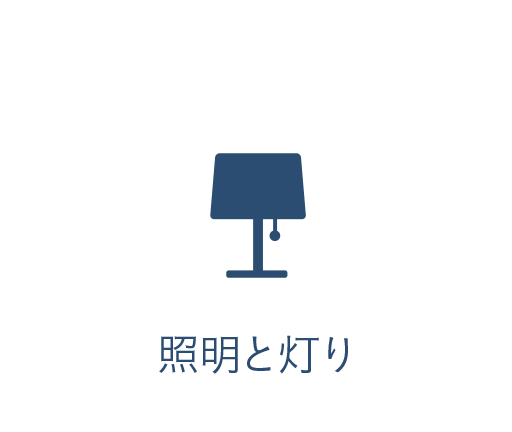
「灯りたまり」は、空間にバリエーションを生みだします
日暮れどきに、一軒の家の前を通り、リビングから温かいオレンジ色の灯りが漏れている風景をみると、楽しそうな家族のだんらんが浮かび上がり、やんわりこころがあたたかくなり、なんともうれしい気持ちになります。
灯り(照明)というのは「心地よい住まい」にとって、とても重要な要素です。
ですから、設計にあたっては、灯り(照明計画)にも非常に神経を注ぎます。
灯りの善し悪しにより、部屋の雰囲気はまったく違ったものになってしまいます。味気のない部屋にもなるし、心地のよい部屋にもなるのです。
落ち着いていて、ゆったりしていて、柔らかな眠りへと導いてくれるような部屋は、決して明るすぎません。
人生の3分の1は、睡眠時間です。コウコウと明るい空間では、体も心も休まりません。
オフィスのように、気を張って仕事に取り組むようなスペースであれば、蛍光灯をたくさん設け明るくするでしょう。
しかし、家は住まう人の憩いの場である以上、必要以上に明るくする必要はないのです。灯りを効果的に使うという発想で生活すると、夜は夜の楽しさがあり、生活も豊かになります。
落ち着いた空間は、「灯りたまり」が低く計画されています。照明の位置が低いのです。
普段、家でくつろぐ時は、座っていたり横になっている時間が多いので、灯りの重心は低い方が落ち着くのです。スタンドライトは、床に灯りが向けられるので、まぶしくなく、灯りの重心が低くなります。
スポットライトも重宝します。スポットライトは向きが変えられるので、その時々の気分に合わせて、灯りのスポット(たまり)を変えることができるのです。


昼は昼の、夜は夜の雰囲気があると、生活が豊かになります。
昼は「太陽による光」であり、夜は「照明による陰影」です。
昼と夜は同じでなくてもいいのです。
単調でまんべんなく明るい部屋というのは、味気がなく、つまらないモノになります。
暗いところ、明るいところといったように、灯りの陰影をつけることにより、人の居場所にもバリエーションが生れます。


照明器具はなるべく、シンプルなモノが良いでしょう。
お気に入りの照明器具であれば、インテリアのポイントになるから良いですが、華美で複雑なデザインの照明は、後々うっとうしく感じるものです。
照明器具の存在感はできるだけ消したほうが、スッキリした空間になります。
これはlouis poulsen※のペンダントライトです。
北欧は、光・灯りを上手に取り入れ、灯りたまりを大切にしています。
ライトを下から覗いても光源(電球)が見えないので、まぶしくありません。また、いく重にも重なる笠で光が拡散され、とても柔らかな光となります。
シンプルで実に良く考えられたライトです。
※louis poulsen = デンマークで設立された照明ブランド

家は、ほんのり暗いほうが、落ち着いた心地よい住まいとなるので、必要以上に照明の数を多くすることはないのです。(暗くするこということではありません。)
数が多ければ、器具代も電気工事代もかかります。
間接照明は、たくさん設ければいいというものでもありません。
シティホテルのラウンジような広いスペースであれば、たくさんあってもいいでしょうが、考えもせずに設けただけであれば、なんだか間延びした空間になってしまいます。
床に向けた間接照明は、床の広がりが感じられ、部屋が広く感じられるので、有効に働きます。
要所要所でアクセントのように計画しています。

リビングとキッチンの12cmのほんの少しのスペースを利用して造った飾り棚。飾り棚により、リビングとキッチンを分離しています。
飾り棚には、メモや、はさみ、爪切りなどの日用品などを置いても便利に使えます。
「造り付け家具」を造るのと造らないのでは、当然、造る方が建物の予算はあがります。
しかし、何もない部屋では住みだしてから家具を買うことになります。
造り付け家具だからといって、後から購入する家具よりも「高い」訳ではありません。造り方次第で、コストもリーズナブルにできるのです。
家具を壁として考え、プラン(間取り)を考えることもあります。造り付けの家具で、空間を仕切り分割するのです。壁を造る必要もなく収納量も増えるので、予算面においても機能面においても「空間の質」はアップします。
このように家を全体予算で考え設計を行えば、無駄なすき間ができずスペースを有効活用でき、心地よい家となります。
心地よい家づくりには、家具のことも最初からしっかり考えて計画しましょう。
照明という観点からすれば、照明を固定してしまうというのは何だかそれだけで、生活のパターンというか、人の行動が限定されてしまう気がします。
例えば居間なら、文字通りただ居る所で、そこで何をするかなど限定するモノでなく、いろいろな居場所になればいいと思います。
居間全体に灯りの陰影があって、読書や何かの必要ができたときには、スタンドをもちだし、手元や必要なところを明るくする、といったようなコトではないでしょうか?
「灯りたまり」は、空間にバリエーションを生みます。